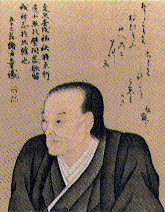一日使って、医学伝記事典(Dictionary of Medical Biography)の緒方洪庵の項目を書いていた。何か論文を書いているときにはブログの更新が滞る。(学会が二つあった6月の更新は悲惨である。)それなら、書いたことや、書きたかったけど書けなかったことをブログに書いてみようか、という苦肉の策。
緒方富雄さんが少し書きにくそうに書いているけれども、洪庵の適塾の医学教育の水準は、当時の水準で言っても決して高くない。オランダ語の習得を中心に学級が組まれていて、その中に物理や化学、軍事や産業技術などと並んでオランダ語の医学書の講読があった程度である。人体解剖はもちろん、動物解剖も、福沢の記述を読む限りでは(クマの解剖のエピソード)、アドホックにしか行われていない。医学の専門学校ではなく、語学の習得と、それによって可能になるヨーロッパの文明一般、特に科学技術系のことがらについての学問を教えることを優先したのは、洪庵自身が意識的に目指していたことでもある。このあたりのことは、蘭学研究者にとっては常識に属することなのだろう。 (私には目新しかったが・・・)
項目を書いていて気になったのは、洪庵のこの適塾の経営方針は、幕末の開国にともなう蘭学・洋学ブームが要請した新しい需要への対応であると同時に、儒学・漢方医学が伝統的にひきずってきた問題そのものでもないだろうか、ということである。伝統的に、儒学と較べたときに、医学は「小技」として軽蔑されてきた。後者は個人を治し、前者は社会と国家に正しい道を示す、というお決まりのロジックである。医者たちの中で野心的なものにとっては、これは辛い。そういったものは、医学を修得して得た知的な資産を、医学以外のこと、とりわけステータスがより高い「男子一生の仕事」に使って名を得たいという目標を持ったと想像できないだろうか。このあいだ読んだ小説によると、医者の家に生まれた橋本佐内は、生業は医であっても、志は別にあり、というようなことを14歳のときに書いたという。佐内は蘭学を選んだが、これは蘭方・漢方を問わず、医学という職業一般が抱えていた問題ではないだろうか。だから、洪庵が推し進めた、蘭方医学から文明学としての洋学へという流れは、江戸時代の医学が伝統的に抱えていた構造の帰結であって、能力があるもの・大志を抱いた少年が、医学の習得を通じて得たスキルを使って天下国家に有益な「大技」を行おうという伝統的な需要に応えた結果ではないだろか。 最近流行の大学の制度改革の口ぶりを真似して言うと、江戸時代の医学は、有為な青年の一般教養だったのだろうか。
項目を書いていて気になったのは、洪庵のこの適塾の経営方針は、幕末の開国にともなう蘭学・洋学ブームが要請した新しい需要への対応であると同時に、儒学・漢方医学が伝統的にひきずってきた問題そのものでもないだろうか、ということである。伝統的に、儒学と較べたときに、医学は「小技」として軽蔑されてきた。後者は個人を治し、前者は社会と国家に正しい道を示す、というお決まりのロジックである。医者たちの中で野心的なものにとっては、これは辛い。そういったものは、医学を修得して得た知的な資産を、医学以外のこと、とりわけステータスがより高い「男子一生の仕事」に使って名を得たいという目標を持ったと想像できないだろうか。このあいだ読んだ小説によると、医者の家に生まれた橋本佐内は、生業は医であっても、志は別にあり、というようなことを14歳のときに書いたという。佐内は蘭学を選んだが、これは蘭方・漢方を問わず、医学という職業一般が抱えていた問題ではないだろうか。だから、洪庵が推し進めた、蘭方医学から文明学としての洋学へという流れは、江戸時代の医学が伝統的に抱えていた構造の帰結であって、能力があるもの・大志を抱いた少年が、医学の習得を通じて得たスキルを使って天下国家に有益な「大技」を行おうという伝統的な需要に応えた結果ではないだろか。 最近流行の大学の制度改革の口ぶりを真似して言うと、江戸時代の医学は、有為な青年の一般教養だったのだろうか。