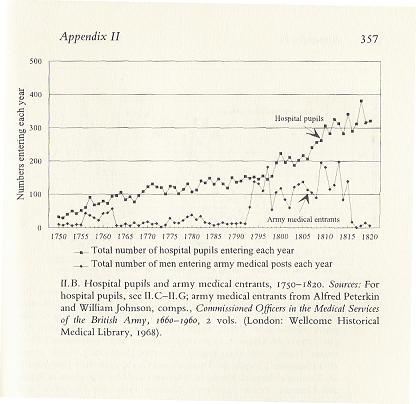必要があって18世紀ロンドンの病院における医学教育のありさまを研究した書物を読む。文献は、Lawrence, Susan, Charitable Knowledge: Hospital Pupils and Practitioners in Eighteenth-Century London (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
医学教育がどのように行われていたかという問題は、しばしば医学史の中心的な問題となる。ミシェル・フーコーの『臨床医学の誕生』は、基本的には1780年から1830年のパリの医学教育に素材にして、深遠な思索を展開したものである。パリの臨床医学革命もそうだが、近代医学の歴史は、かつては全く別の職業であった内科と外科が統合されていく過程でもあった。中世においては、内科は大学で教育されていて、法律家・聖職者と同じジャンルの教養ある専門職であり、外科は徒弟修業で訓練されていて、大工や鍛冶屋と同じジャンルの職人であった。外科医はもともと床屋と同じギルドに入っていた、あるいは同一の個人が外科もやれば床屋もやっていたという逸話は多くの人に知られている。内科医から見た時、外科は手仕事に携わる低級な職業であり、自分たちが命じた瀉血などをする<はしため>であった。内科医で、フランス王ルイ14世の侍医であったギー=クレッサン・ファゴン(Guy-Cresent Fagon, 1638-1718)が、膀胱結石をある外科医に取って貰い、外科医が術後の養生についてアドヴァイスしたときに、ファゴンは「私が必要としたのはあなたの手であって、頭脳ではない」と寸鉄刺すような返事をしたというエピソードは、当時の内科医が外科医に対して持っていたイメージを象徴している。
しかし、18世紀の初頭から、外科医が、内科医とは自らを区別しつつも、<体系的な知識に基づいた教養あるわざ>を持つ専門家としての性格を強めるようになる。一言で言うと、個々の親方から見よう見まねで憶えていく技能ではなくて、科学に基づいていて、スタンダードな職能としての外科が形成されていく。この過程にとって、「病院」という場が非常に重要な役割を果たしたことは良く知られている。