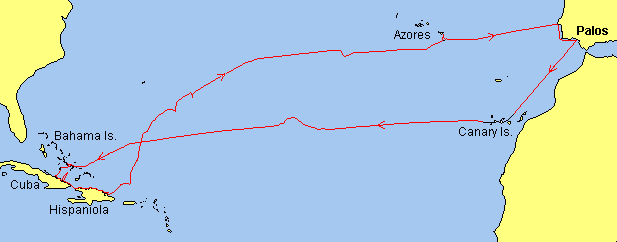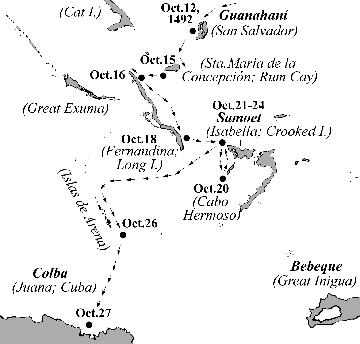コロンブスというのは狡猾なところとナイーブなところが共存している男だなと思った。表帳簿と裏帳簿のような記述で、その日に進んだ距離(「30レグワ」とか)を、船員には偽の数字にして教え、新大陸への厳密な航路はコロンブスしか分からないようにしてある。さすがに生き馬の目を抜くイタリア人の山師船乗りだなあと感心する。この狡猾な男が、その一方で、血眼になって黄金を探していることを原住民に隠しもしないナイーブさはよく分からない。
この男たちは、黄金を捜しているのだということは、すぐに現地でも話題になっていたことが伺える。インディオたちに場所を教えてもらって、航海者たちは黄金探しに血道を上げる。このテキストを編集しているのは後に『インディオスの破壊についての簡潔な報告』でスペイン人たちを告発するラス・カサスだが、非常に抑制が効いた彼の註に、嫌悪と軽蔑と恥の意識が行間ににじみ出ているような気がするのは、読み込みすぎだろうか? たとえば、コロンブスたちが黄金の粒を見つけて「リオ・デ・オロ」と名づけた河について、ラス・カサスはこのように註をつけている。
「自分は、この川にあったものの多くは、この地方に多量に産するマンガンだったと思う。おそらく提督 [=コロンブス] は、光るものは全て黄金だと思ったのであろう。」
・・・ラス・カサス君、スペイン人にしては、洒落た物の言い方を知っているじゃないですか(笑)。言われてみたら、『インディアスの破壊』も淡々と押さえた筆致だった。
一つ非常に失望したことがある。岩波文庫のこの翻訳には、地図が「一枚も」ない。確かに、オリジナルにもないのだろうし、コロンブスの航路について学術上の論争があって、決定版の航路を記した地図を載せられないという事情はわからないでもない。しかし、地図がない航海誌や旅行記というのはちょっとした衝撃であった。