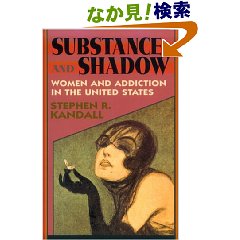必要があって、女性に焦点を当てたアメリカの薬物依存症の歴史の研究書を読む。文献は、Kandall, Stephen, Substance and Shadow: Women and Addiction in the United States, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996). 著者は薬物依存症の治療のスペシャリストの医者だけれども、有能なアシスタントを使って多数の文献を集め、基本的な史実と鳥瞰図を安心して読める仕方で提示し、さらには現場を知るものならではの自信と洞察がちりばめられている。日本の人文社会系の医学史の研究者には、「医者が書く医学史」を軽視する風潮があって、確かに軽視されてしかるべき研究もあるけれども、アメリカやイギリスでは「医者ならではの医学史」で読み応えがあるものが沢山あるし、日本でもそういう仕事がないわけではない。
現代までカバーしている本で、きっとそのあたりが読み応えがあるのだろうけれども、1914年のハリソン麻薬法 (Harrison Anti-Narcotic Act) の前後を扱った章を集中的に読む。
19世紀にわたって、アヘンやアヘンチンキ、あるいはアヘンから抽出したモルヒネは、医者が最も多く処方した薬であり、人々は医者の処方を通じてアヘン依存症に陥っていった。多くの戦傷者が出た南北戦争などの後には、傷の痛みを和らげるために大量に処方されたアヘン系の薬の効果で、依存症もたくさん出ているという観察がされている。実際、モルヒネやコカインを自由に入手できた医者や医者の家族の間では依存症の問題も深刻で、ある町の医者100人のうち30-40人が依存症であったという報告もあったという。さらに、市販の大衆薬(というのですね)にも、アヘンや19世紀の末に局所麻酔の効果が発見されたコカインが含まれていて、これらも依存症の原因になった。いわゆる「リクリエーショナル」なドラッグの利用も、中国からの移民労働者がアヘン吸引の習慣をもちこんで(このあたりは異論があるらしい)、アヘン窟がひろまり、また、アヘン窟と並んで設置されることが多かった売春宿でもアヘンのリクリエーショナルな吸引が広まっていた。19世紀の末になると、依存症の危険が叫ばれ、医者たちの間でも論争がおきる。1910年には全国で100近くの麻薬依存症を治療をするための施設があったという。4週間から8週間が入院の相場だったそうだ。
このなかで、19世紀においては、典型的な依存症患者のプロフィールは、中産・上流階級の女性だった。いつの段階でどう取られた統計なのか、この本には書いていないけれども、ある研究によれば、依存症患者の2/3 から 3/4 は女性だったという。この理由は、医者たちが持っていた「女性の体は繊細で弱いから、医学と薬で守って上げなければならない」という思想であったという。特に、月経・妊娠・出産などの現象にともなう痛みや不調に対しては、大量の鎮痛剤が処方された。頭脳労働や心理的な緊張や精神の過活動によっておきるとされた神経衰弱は、薬物依存の原因でもあり、結果でもあると考えられていた。これも、中流・上流階級の病気であった。
1909年に雑誌に掲載されたという、あるモルヒネ依存症の女性の言葉が、面白いヒントを含んでいた。
「モルヒネは、真実に<夢>を与えてくれるのです。真実だけでは私たちには不満足が残りますし、また、重荷になりすぎます。一人ひとりが、真実に、自分自身の<夢>を付け足さなければならないのです。だから、私は、モルヒネを服んで自分の夢を足したんです。そうして、<自分の人生>を可能にしたんです。」
薬物依存症が、このように魅力的な哲学的・文学的な考察ができる中流・上流階級の問題だったときは、人々はその存在を黙認していた。しかし、これが都市下層民や貧困・移民・犯罪と結び付けられるようになると、国家としての対策が始まったという。
図版は本書のカヴァーとイラスト。中流・上流階級の女性の薬物依存症を描いている。