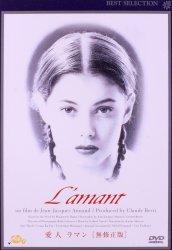マルグリット・デュラスの『愛人(ラマン)』を読む。河出文庫の清水徹訳。仕事で必要な部分だけあさって読むはずが、思わず引き込まれて熱心に読んでしまう。清水の文庫版解説は出色で、すごく得した気分になった。
マルグリット・デュラス(筆名)は、1914年にフランス領インドシナのサイゴン近郊に生まれる。両親は二人とも学校教師をしていたが、デュラスが4歳の時に父親は死に、残された母親は学校教師をしながらデュラスと二人の兄を現地で育てる。土地経営の失敗などから、一家は植民地の貧しい白人としての生活を余儀なくさせられる。デュラスが18歳の1932年に、デュラスは高等教育を受けるためにパリに帰る。この小説は、デュラスがサイゴンの寮に住みリセに通っていた15歳の時に出会った、裕福な中国人男性と出会い、身体の関係を重ねるありさまに、母と二人の兄の思い出(特に下の兄がデュラスの愛情の対象だった)を交錯させた小説である。15歳の少女になって当時の思いが一人称で語られる部分と、執筆当時から追憶した時制で語られる部分が交互に現れて、その混在が非常に魅力的な語りを作り出している。小説として純粋に面白かった作品を、仕事のネタに使うのは気が引けるけれども、ここでは研究の話をさせてください。
ここで描かれているのは、熱帯の植民地に移民した第一世代と第二世代の懸隔である。母親はフランスのロワール県の生まれであるのに対し、子供たちは―少なくともデュラスは―ベトナムで生まれている。この「生まれ」の違いは母親を不安にさせた。自分の子供たちがフランス人としてのアイデンティティを失って、現地人に同化してしまうのではという不安である。この同化への不安は、文化や言葉や習慣の問題だけではなく、身体にも及んでいた。インドシナの土地に生まれ、その気候の中で暮らし、その太陽をあび、その食物を食べると、インドシナ人の身体を持つようになってしまうのではという不安である。この概念は「馴化」と呼ばれ、違う土地に移住した人間がその気候に適合して健康に暮らすことができるというオプティミズムを可能にしたと同時に、アイデンティティの危機を意味するものでもあった。
この馴化が前提している可塑的な人種概念とは大きく異なった、より固定的な概念が「遺伝」であり、この遺伝概念は、すでに科学者たちが研究し、一般にも喧伝されていたが、人々の意識のなかでは「馴化」の概念は深く根付いていた。デュラスが想起する彼女の母親の不安と少女時代の彼女の想像は、馴化の概念に色濃く染まっている。デュラスは、母親の意向に反して、フランスの果物であるリンゴを吐き出し、母親が眠っている間にマンゴーをたらふく食べる。母親が強いるパンではなくて、米が彼女のお気に入りである。コレラにかかるからと禁止された沼地の魚を食べ、肉は吐き出してしまう。これらのベトナムの食べ物、「不潔な食物」でできた体を持つ彼女と小さいほうの兄は、やせた、小さな子供であり、「白人というより黄色人種に近い」。精神が不安定だった母親が怒った時には、デュラスと兄を「汚らしい安南のチビ」と呼んでいたという。
この、インドシナの風土に同化したデュラスの身体は、母親には嫌悪が混じった感情を惹き起こしたが、彼女の愛人である中国人にとっては、惹き付けられる何かを持っていた。パリに留学したことがある彼は、フランスの気候と水と食物で育った女に比べると、デュラスの体は親近感を持てるものだったのである。
「彼は言う、この国で、この耐え難い緯度で何年もの年月をすごしたために彼女はこのインドシナの娘になってしまった。この国の娘たちのようなほっそりとした手首をしているし、この国の娘たちの髪と同じように、まるで張りのある力の全てを引き受けて身につけてしまったかのような、濃く、長い髪をしている。とりわけこの肌、全身の肌といったら、この国で女や子供たちのために取っておく雨水を使っての水浴を経験してきた肌だ。彼は言う、フランスの女たちの身体の肌は、この国の女たちとくらべると、固く、ほとんどざらついている。彼はさらに言う、魚と果物だけの熱帯の貧しい食物も、それにいくらか役立っている。(後略)」
熱帯の太陽と水と食物は、彼女の体を、同じく熱帯で育ったその中国人の男の体と「類似性があるもの」にしたのである。どちらの家庭からも全く祝福されなかった中国人が彼女に対して抱いた狂おしい愛情の一部は、自分の体との類似性であっただろう。
この原作に基づいた有名な映画がある。いつものことで申し訳ないけれども・・・って、あとは略してもいいですね(笑)