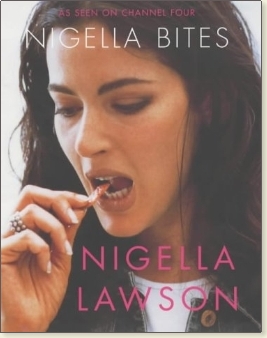本当はこんな本を読んでいる時間はないのだけれども、新着本を読み始めたら止められなくなってしまって、一時間ほどかけて面白い章を二つ読んでしまった。文献はHughes, Kathryn, The Short Life and Long Times of Mrs Beeton (New York: Anchor Books, 2007). 著者は、水準が高いベストセラーの歴史や伝記を幾つも書いている、イギリスで人気のノン・アカデミックな歴史家。
伝記の主人公はイザベラ・ビートン (Isabella Beeton, 1836-1865)で、1859年から出版が始まった『ビートン夫人の家政大全』(Mrs. Beeton’s Book of Household Management)で名高い。『家政大全』は、ヴィクトリア朝イギリスの中産階級のイメージを象徴するテキストである。クリノリンのスカートをはいて、使用人を監督して家族のための料理とこまごまとした家政に没頭する主婦たち。「肉の悦び」を悪魔の誘惑のように恐れる彼女たちが供する、料理をまずくするツボを知り尽くしたように、これ以上まずい瞬間はないなまぬるい温度で出てくるお料理。茹ですぎの野菜と、下水を思わせるスープ。モダニズムとフェミニズムとグルメブームの共通の敵があるとしたら、それは間違いなく『ビートン夫人の家政大全』だろう。このシンボリックなテキストとその著者を、当代一流のイギリスの人気歴史家が取り上げて、数年間のリサーチを経て満を持して書き下ろした書物が、面白くないわけがない。
ヒューズの書物から現れるビートンとその書物は、ステレオタイプとはがらりとイメージを変えている。確かに野菜はゆですぎだけど(ニンジンは二時間半ゆでろとのこと・・・涙)、あの悪夢のような料理を供する野暮ったいイギリスのおばさんが書いた家庭レシピとは全く違ったものである。この書物を書き始めたときに、ビートン夫人は22才か23才で、出版社を経営し、雑誌の編集者だった夫のに嫁いだばかりだった。夫が編集するイギリスの主婦雑誌のために、既存の女性向け実用書や、上流階級向けのフランス人シェフが書いた料理書などから、臆面もなく盗用して作り上げたのが本書だった。妻としての経験は非常に浅く、母としての経験は事実上なかった女性がパスティーシュで作り上げたのが「家政大全」だったのである。
この書物は、当時の多くの女性たちの心を掴んだ。ヴィクトリア時代の<分離された領域>の中で、多くの中産階級の女性にとって、家事は、彼女の能力を試され、その成功に自己実現と市民としての義務の履行がかかったシリアスな営みになっていた。中産階級の女性たちは家事を使用人に任せていたというのは、理論上はそうであったというだけであって、非熟練の使用人を一人雇うのが精一杯の大多数の中産階級にとって、女主人も家事に参加する必要があった。(ビートンの書物の冒頭で、年収を五つのランクに分けて、それぞれのランクで何人の使用人を雇うことができるかが詳細に述べられている。)その状況で、科学的な知識に即して(「ジャガイモの75.52%は水分で、15.72%は澱粉である」とビートンは誇らしげに書いている)、合理的な「システム」にのっとって家事を成功させる方法を説く『家政大全』は、同時代の支配的なトレンドと同じ方法で家事を行う方法を説いていた。収入とランクを気にしながら、自分の母親たちが経験していなかった仕事で、自己の能力を試される新しい「家事」(ホームパーティはその代表である)をしなければならない不安を抱えていた新しい主婦にとって、『家政大全』はまさに福音であった。家事は、男性が家の外でする仕事と同じように、シリアスなものになったのである。これは、家事のステータスを上げ、それに責任を持つようになった女性たちに、男性とパラレルな「職業」を与えることになった。